診療体制
放射線診断科
- 概 要
- IVR
- 核医学治療
- 医師紹介
- 医療機器
診療概要
放射線診断科はX線写真、CT、MRI、核医学(RI)などの画像診断と、画像ガイド下で行う治療手技「インターベンショナル・ラジオロジー(IVR)」を行っています。「救急センター」に隣接することで救急搬送された患者さまの検査を速やかに実施します。検査機器はの定期的なリニューアルにより高度でより迅速な検査が可能です。
放射線科医は、毎日多くの画像を読影し画像診断報告書を作成することで、臨床診断を確定診断へ導くサポートをしています。また、検査や直接治療するIVRなどを行っています。診療放射線技師は、各種画像検査において被ばく低減をはじめ装置の操作や管理など安全性の確保に努め、医師・看護師と連携して早期診断・早期治療に役立つ最善の画像を提供しています。そして医療チームの一員として専門知識を生かすことはもちろん、患者さまに安心して検査を受けていただけるよう笑顔で対応し、納得のいく説明を心がけています。
- 静音化対応のMRIにより、弱い麻酔、あるいは麻酔無しで小児の検査ができます。
- 女性特有の検査(マンモグラフィや乳房MRI)には女性技師が対応します。
スタッフ体制
(2025年4月現在)
- 放射線科医 16名(常勤+非常勤)
- 放射線診断専門医 12名(うち常勤3名)
- 放射線医 4名(うち常勤1名)
- 診療放射線技師 51名(男30名・女21名)
- 放射線科看護師 7名
保有資格
- 放射線管理士 9名
- 放射線機器管理士 9名
- 臨床実習指導教員 5名
- 救急撮影認定放射線技師 4名
- X線CT認定技師 5名
- 肺がんCT認定技師 1名
- 磁気共鳴専門技術者 2名
- 核医学専門技師 1名
- 日本血管撮影・インターベンション専門診療放射線技師 2名
- 医療情報技師 3名
- 第一種放射線取扱主任者 4名
- 第二種放射線取扱主任者 1名
- 放射線治療専門放射線技師 1名
- 放射線治療品質管理士 1名
- 検診マンモグラフィ撮影認定放射線技師 9名
- 胃がん検診専門認定技師 1名
- 医療画像情報制度管理士 2名
- 超音波検査士(消化器) 1名
- 超音波検査士(循環器) 1名
- 医療経営士2級 1名
- 医療経営士3級 2名
- 医療福祉接遇マナーインストラクター 1名
- Ai認定診療放射線技師 2名
- 画像等手術支援認定診療放射線技師 1名
- ピンクリボンアドバイザー中級 1名
- ピンクリボンアドバイザー初級 5名
- 医療安全管理者 1名
- ICLSインストラクター(日本救急学会認定) 1名
施設認定
- IVR被ばく低減認定施設(全国循環器撮影研究会)
- 日本放射線腫瘍学会認定施設(日本放射線腫瘍学会)
- 治療用照射装置出力線量の測定実施施設(医用原子力技術研究振興財団)
- マンモグラフィ検診施設・画像認定施設(NPO法人日本乳がん検診精度管理機構)
- 胸部X線撮影・胃部X線検査 精度管理評価実施施設(全国労働衛生団体連合会)
インターベンショナル・ラジオロジー(IVR)
X線透視、CT、MR、超音波などさまざまな画像診断装置で身体の中、血管の様子などを見ながら、細い管(カテーテルや針)を入れて、標的となる病気の治療を行います。どこを治療するかを正確に把握して、身体への負担の少ない治療を行うことができます。
血管の拡張、ステントの留置、止血、がんに栄養を共有する血管の封鎖、抗がん剤の直接注入、ドレナージ(腔にたまった滲出液・膿・血液などを排出する治療)など、さまざまな治療法があり、各科と連携して提供しています。
主な治療
緊急IVR
大出血時の原因検索・止血による救命
血管内治療
動脈塞栓術(TAE)、経皮的血管拡張術(PTA)、血管ステント・ステントグラフト留置など、血管外科、循環器内科、腎臓内科などと連携して、腹部や四肢における処置を行っています。動注化学療法、下大静脈フィルター、門脈系IVR(TIPS、B-RTO)などにも対応しています。
抗がん剤注入TACE
肝動脈化学塞栓療法(Transcatheter Arterial Chemo-embolization)も施行可能です。
CVポート、末梢挿入中心静脈カテーテル(PICC)留置
当院から退院されて在宅で栄養状態を安定させて療養されたい患者さま、他院よりご紹介いただいた患者さまなどに、合併症を起こさない安全なポート留置を実施しています。小児にも数多く対応しています。
そのほか、IVRを必要とする患者さまに対し、各診療科と連携し、安全かつ迅速な治療を提供いたします。
造影剤について
当院ではCTやMRIなどの検査の際に、必要に応じて造影剤を使用しています。造影剤を注射することで血管・臓器・病気の部分などの様子が分かりやすくなり、より正確な診断を行うことができますが、一方で、副作用が起こることがあります。造影剤を使用する際には、患者さまに事前にチェックリストを記入いただき副作用の予測を図っていますが、完全な予測は不可能です。
副作用の症状は、吐き気・発疹などの軽症のものから、呼吸停止などの重篤なものまであり、発症時期も造影剤投与直後から数時間以上経って発症するものまでさまざまです。重篤な副作用が起こる確率は非常にまれですが、決して100%安全な検査ではないことをご承知おきください。
造影剤の副作用
軽い副作用
吐き気、動悸、頭痛、かゆみ、くしゃみ、発疹などで、基本的には治療は必要ありません。このような副作用の起こる確率は5%以下です。
重い副作用
呼吸困難、意識障害、血圧低下、腎不全などです。このような副作用は、入院の上、治療が必要なことがあり、場合によっては後遺症が残る可能性があります。このような副作用の起こる確率は約0.02%です。また、病状・体質によって約10~20万人につき1人の割合で死亡例の報告もあります。
注意が必要な方
喘息やアレルギー体質の方は副作用のおこる確率が高いといわれています。また、造影剤は腎臓から排出されるため、腎機能の悪い方ではさらに悪化させる可能性があります。これらの方には造影剤を使用できないことがあります。妊娠・授乳中の方については造影剤の使用について慎重に検討いたします。
ご不安な方はご相談ください
現在、副作用の発生を予測する確実な方法はありません。過去の検査で副作用がおきなかった方にも副作用がおきる可能性があります。造影剤を使用したくない、また、使用することにご不安な方は、担当医または放射線診断科スタッフにお気軽にご相談ください。
造影剤副作用カード
患者さまの身におきた造影剤による副作用の再発を防止するためには、医療機関と患者さまの両方で情報を共有することが大切です。当院では、日本放射線専門医会が制作した「造影剤副作用カード」を採用しています。このカードは副作用の再発を防止し、患者さんを守ることを目的として制作され、全国で普及が図られているものです。CTやMRIなどでの造影剤を使用した検査において、副作用が発生した患者さまにお渡ししています。
このカードをお持ちの患者さまは、ご自身で大切に保管し、当院または他院での検査の際には必ずご提示ください。複数の医療機関で副作用の情報を共有することができ、再発防止に繋がります。
ゾーフィゴ治療
前立腺がんの骨転移に対する治療の1つで、「ゾーフィゴ静注」という薬を注射します。症状の緩和や延命効果が期待できます。主に去勢抵抗性前立腺がん(ホルモン療法を実施しても症状が悪化する前立腺がん)に対して行います。
ゾーフィゴ静注とは
ゾーフィゴ静注には「ラジウム-223」という放射性物質が含まれています。ラジウム-223にはこのような特徴があります
① 骨に集まりやすい
骨の成分であるカルシウムと似た性質をもち、骨に集まりやすいという特徴があります。注射で体内に送られると、代謝が活発になっているがんの骨転移巣に多く運ばれます。
② アルファ線と呼ばれる放射線を出す
アルファ線は、X線などと比較して細胞を破壊する力は強いものの、力が届く範囲(ダメージを与える範囲)は小さいのが特徴です。そのため、骨転移巣に運ばれ放出されたアルファ線は、骨に転移したがん細胞には大きなダメージを与え増殖を抑えながらも、正常細胞に影響を及ぼすことは比較的少ないとされています。
副作用
注意が必要な副作用
骨髄抑制(骨髄機能が低下し血液細胞が減少すること)
その他の副作用
悪心・嘔吐、下痢、食欲減退、骨の痛み、疲労など
治療期間
1カ月に1回の注射を行い、最大で6回の治療を行います。外来での治療が可能です。
なお、骨髄抑制の有無や程度を確認するため注射前は血液検査を実施します。また必要に応じて治療期間中は血液検査を行います。
費用
最大6回の治療で約400万円(※高額医療費制度が利用できます)
当院で治療をお考えの方へ
ゾーフィゴ治療は、骨転移を有する去勢抵抗性の前立腺癌かつ骨以外の内臓転位が無い方が対象です。患者さまの状態や病気の種類によって適応・不適応がございますので、泌尿器科医が診断のうえ治療の適応かどうかを判断いたします。まずは泌尿器科外来を受診し、主治医にご相談ください。
管理医師
山之内和広 放射線診断科部長

- 所属学会
- 日本医学放射線学会、日本放射線科専門医会
- 資格
- 日本医学放射線学会認定放射線診断専門医、厚生労働省緩和ケア研修修了医
- 専門領域
- 放射線診断
泉雄一郎 放射線診断科部長
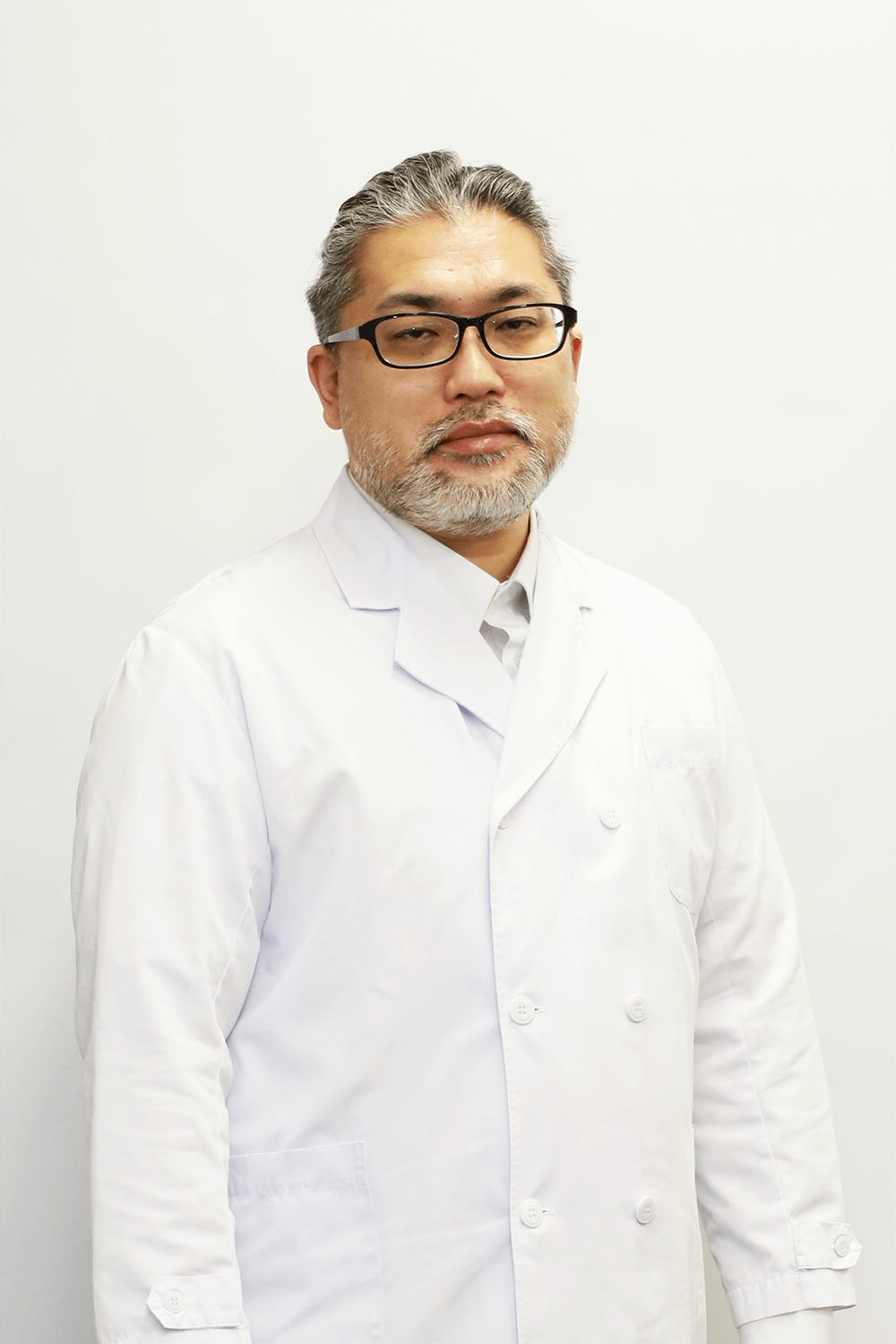
- 所属学会
- 日本医学放射線学会、日本IVR学会
- 資格
- 日本医学放射線学会認定放射線診断専門医、日本IVR学会IVR専門医
- 専門領域
- 放射線医学
スタッフ医師
- 鶴田千絵
-
- 所属学会
- 日本医学放射線学会
- 資格
- 日本医学放射線学会認定放射線診断専門医
- 専門領域
- 画像診断一般
CT 装置
Aquilion ONE Vision Edition(大同病院)
広範囲をあっという間に撮影する320列CT装置
320列CT装置は1回転で広範囲を撮影でき、さらに高速回転も可能になったことで撮影時間が短縮され、心臓CTで息止めが難しい患者さまや動いてしまう小さなお子さまでも対応することができます。
また、被ばく低減技術「AIDR3D」が標準搭載されており、当院の従来CTと比較して最大75%の被ばく低減が可能になりました。
主に救急患者さま、入院患者さまの撮影と外来の造影検査を行っています。

Aquilion ONE Vision Edition
Aquilion PRIME(だいどうクリニック)
コンパクトなのに高性能な80列CT
CT装置本体が少し小さいサイズに設計されているため、従来に比べ撮影室へ入った時の威圧感が少ないです。
また、被ばく低減技術「AIDR3D」が標準搭載されており、当院の従来CTと比較して最大75%の被ばく低減が可能になりました。
主に外来患者さまの当日・予約検査に対応し、健診の肺ドックも撮影しています。

Aquilion PRIME
MRI装置
Ingenia Elition 3.0T(大同病院)
高画質かつスピーディに撮影するMRI装置
従来型MRIと比べて非常に高画質で、速く検査を行うことができます。
また、静音化技術によって最大80%検査音が低減されたほか、患者さんの快適性を追求した寝台なども備えています。

AERA 1.5T(大同病院)
広くて静かなMRI
内径が70cmと広いことで患者さまに安心感を与え、今まで狭いと感じていた患者さまも快適に検査を受けることができます。
新たな静音技術「Quite Suite」により騒音を今までの70%以上低減し、乳児・小児は弱い麻酔あるいは麻酔なしで検査を行うことができます。
主に小さなお子さまや他院からの紹介患者さまの検査、造影検査を行っています。

ESSENZA(だいどうクリニック)
コンパクトなMRI
クリニックの外来MRI検査用に設置し、健診センターの脳検査(旧・脳ドック)にも対応しています。

血管撮影装置
Allura Clarity FD10/10
高画質で低線量の心臓専用装置
心臓血管撮影では、冠動脈の状態を把握するために多方向から撮影を行います。そのとき撮影を行う回数分の造影剤注入が必要となります。 この血管撮影装置は撮影アームが2本あるため、一度の造影剤注入で2方向の撮影を行うことができ、患者さまの負担を軽減します。 また、Clarityシリーズは従来の血管撮影装置の約70%の大幅な被ばく線量低減を実現し、治療をより安全に行うことができます。

Allura Clarity FD20/15
腹部や四肢もカバーする大視野血管撮影装置
大口径のフラットパネル検出器のため、頭部から下肢まで全身領域をカバーできます。 さらに回転撮影によって、3Dの血管像を描出する機能(3D-RA)とCT画像と同様の軟部組織イメージングを得ることができます(XperCT)。 ライブ透視画像とCTやMRIの画像を合成して表示でき、また、1枚のディスプレイにさまざまな画像を映し出した状態で手技を行うことができるため、IVRなど高度な治療を可能にした血管撮影装置です。
また、Clarityシリーズは従来の血管撮影装置の約70%の大幅な被ばく線量低減を実現し、治療をより安全に行うことができます。
被ばく低減への試み
当院は2013年8月に「全国循環器画像研究会 被ばく線量低減施設認定」を取得しました。

放射線治療装置
高精度放射線治療システム
当院では、「がん細胞」に集中して放射線を照射し、正常な組織への副作用を低減させながら、高い位置精度で照射する高精度な放射線治療を実施しています。病巣が脳や脊髄などの重要な臓器に接していて照射が難しい症例でもピンポイントに正確な照射をすることができます。
導入機器では、高い線量率で短時間の治療が可能となり、症例に応じて最適な放射線治療を提供します。
治療計画装置には、高速かつ高度な放射線治療計画を可能にするソフトウェア「RayStation」を採用しています。

Aquilion LB
治療用CT
治療計画に必要なCT画像を撮影する16列CT装置です。口径が広いため、体の大きな患者さまにも対応できます。また、寝台は治療装置と同様のカーボンを使用しているため、治療計画に最適な条件でCT画像を得ることができます。さらに、診断用に使用することも可能で、透視下生検や病院CTのバックアップとしても対応しています。

体外式衝撃波結石破砕装置
ドイツで開発された結石破砕装置
腎臓や尿管に沈着した結石に衝撃波を照射して結石を粉砕するESWL(体外衝撃波腎・尿管結石破砕術)を行います。
従来の装置より結石に焦点を合わせる操作が改善されたため、破砕能力が向上し痛みも軽減しています。
外科手術をすることなく日帰り入院で結石を治療できます。

核医学診断システム
Symbia E
より高感度に、より多彩な情報を
従来よりも高感度な検出器を搭載したため、検査時間を短縮することが可能です。従来と同じ検査時間ならば、よりノイズの少ない画像を得ることができます。また、ソフトウェアも充実しており、さらに豊富な情報を提供できるようになりました。
検査室は圧迫感を極力排し、リラックスして検査を受けていただけるよう設計しました。

マンモグラフィ装置
AMULET Innovality(だいどうクリニック)
3D撮影ができるマンモグラフィ装置
トモシンセシス(3Dマンモグラフィ)が撮影できます。 CTやMRIのようにトモシンセシスで断層像を得ることによって、従来は診断の難しかった乳腺に隠れた病変を見つけやすくなります。 また、この装置に導入している画像処理技術「Excellent-m」では、従前よりも30~40%の線量が低減されています。 マンモグラフィ下での生検にも対応しており、がんなどの確定診断をサポートします。

デジタルX線TV装置
CUREVISTA
豊富な情報をマルチディスプレイで
フラットパネルディテクターを採用したX線透視装置です。内視鏡との連携を重視した装置・レイアウトで構成されており、マルチディスプレイに透視画像・内視鏡画像が表示され、安全かつ迅速に検査や治療が可能です。

CUREVISTA Open
新世代画像処理エンジンを搭載し、高画質化・被ばく低減が実現された最新機器
当院に設置されていた従来装置(※日立製作所社製 CUREVISTA)と比較して、VISTABRAIN機能によってノイズ低減され高画質化が可能となりました。この機能によりX線量を多く出す必要がなく、鉛入りカーテンを使用した場合の術者被ばく線量を最大80%低減することが可能となりました(※当院実測値と比較)。当院では主に内視鏡を併用した検査・治療に使用されます。
本機は寝台が固定され、映像系機構が寝台上を自由自在に動きます。検査中に患者を動かす必要がないため術者は手技に集中でき、安全性が向上しました。

Ultimax-i
さまざまな角度から撮影可能
Cアーム付きの透視撮影台により、自由な角度から撮影できます。整形検査から血管造影検査まで幅広いX線検査が可能です。
被ばく低減
画像フィルタ処理や、低レートパルス透視を用いることで、透視・撮影共に以前の装置より被ばく低減を計りました。

一般撮影装置
RADREX + FUJIFILM DR CALNEO C 1717 Wireless SQ
より早く、より低線量に
FPD(フラットパネルディテクター)搭載の一般撮影装置を導入したことにより、即時性が向上し、検査の時間を短縮することが可能となりました。また低線量撮影が実現し、従来の約半分の被ばくで撮影ができます。
患者さまに安心して検査を受けていただけるように、撮影室のスペースを広く取り、壁紙を明るくすることによって閉塞感の軽減を計りました。

骨密度測定装置
PRODIGY C(だいどうクリニック)
高精度な骨密度測定
骨密度測定装置は骨粗しょう症の診断、治療に必要な情報を提供します。また、発病前兆候を発見し積極的予防に寄与します。 当院の骨密度測定装置はDXA法を用いた骨密度測定装置で撮影部位は主に腰椎、大腿骨を対象とし、前腕骨を撮影することも可能です。高精度を保ちながらの高速撮影、被ばく低減を実現しています。

- 診療科の紹介
- 部門の紹介





